ピグマリオン効果を知ろう
舞台はアメリカ、1964年の秋、教育心理学者のロバート・ローゼンタール博士がある実験をしたのです。
9月の新学期の始まりに、アメリカのそっちこっちの小学校に出向いて、子供たちの担任の先生にこう告げました。
★我々が行った「ハーバード式潜在能力検査」の結果、今後1年間で知的成長が著しく伸びると予測される児童がわかりました、あなたのクラスの、この子とこの子です。
担任の先生方はどう思ったのでしょうね。でも、ハーバードという偉い学者先生からの突然の言葉ですから、きっと驚きをもってその言葉を聞いたことと思います。
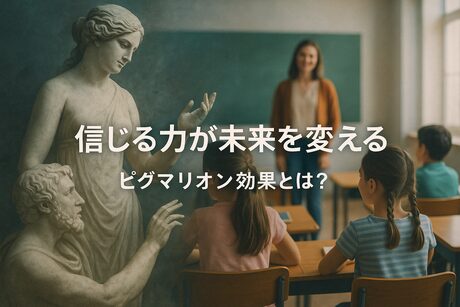
1.でっ、その結果はどうなった?
先生方には言葉で伝えただけだったのです。成績の資料とか生徒の名前を書いたものなど、何もありません。
そしてご想像の通り、名前を挙げた子供というのは、本当はテストの結果とは関係なく、適当に選んだ子供たちだったのです。
ところが翌年春、その学年の終了時点で再度、子供たちの知能テストを行った結果、なんと、名前を挙げられた子供の成績が本当に伸びていたというからびっくりです。
ところで、ローゼンタールと研究者たちは先生方に、
・このことを子どもたちには絶対に言ってはいけないよ
・子どもたちを差別してもいけません。我々はあなたを監視しています
と、きつく言っておいたとのこと。
子どもたちを区別もしない、子どもたちに伝えることもない。なので子どもたちは自分が頭がいいなんて、思いもよらなかったことでしょうね。
それなのに、それなのに、約8か月後には本当にその子どもの成績が伸びてしまったのです。
もちろん偶然ではなく、統計的にも成績が上がったことがしっかり確認されたのです。
まあ、これだけだと「ふ~ん」で終わってしまいそうですね。
2.本当に成績が上がったのかい?
疑い深い人はたくさんいます。いや、そうじゃなくても本当にそんなことがあるのか?と疑ってしまうのは当然ですよね。その子たちの成績は本当に上がったのか?何かからくりがあるんじゃないか?
ということで、この話を聞いたたくさんの研究者たちがその後に同じような実験をたくさんしたんだそうですが、どうやらこうした傾向は本当だ、という実験結果が多かったようですね。
でも、ここでちょっと考えてみましょう。
この実験と同じ実験をもう一度繰り返そうと思っても、そう簡単にはできませんよね、特に日本では。
誰かに勝手に我が子が「頭が悪い」とされたりしたら、きっと黙ってはいない親がたくさんいることでしょう。
過去の心理学実験で、たとえば電気椅子に座らせた「ミルグラムの服従実験」なんてありましたが、倫理上の問題で、こうした実験は今後行ってはいけないということになりました。もっとも、最初に行った実験の価値がとても高いことに変わりはありません。
こうした実験ほどではなくても、ピグマリオン効果の実験もとてもやりにくい実験だと思います。どうやってランダムに成績が伸びる子とそうではない子に分けるのか、分けた結果本当に成績が悪くなったら、実験者は責任がとれるのか。
3.この実験、実はとても奥が深いのです
ということを考えると、ピグマリオン効果の実験は後に続く実験ではなく、最初に行った実験がどうだったのかに興味が向きます。
このピグマリオン効果の実験で、
・・ローゼンタール博士はどうしてこんな実験をしようと思ったの?
・・ピグマリオン効果の実験の前は、どんな実験をしていたの?
・・ピグマリオン効果の実験で、効果があった場合となかった場合の条件の違いは?
・・この実験の被験者は何をどう感じていたの?
こんなことを調べているうち、だんだん抜け出せなくなるような面白さが沸いてくるのです。
ローゼンタール先生は、どうやら心理学の実験のやり方に疑問を持ったようでした。そして、それを確かめるため学生たちとネズミを使って実験をしました。
その結果、「おいおい、これ人間の子供にも当てはまるんじゃないか!」とばかりに、アメリカ各地の小学校での実験となったわけですね。
この実験、実は実験者役の教師や学生の側が騙されているというのが面白いところですが、さらに、ピグマリオン効果の実験で、実際に効果のあった条件とあまり効果のなかった条件を調べてみると、これもまたとても面白いことを教えてくれます。そして、実験者となった学生たちの反応もまた面白いものがあります。
さらにはこの実験、人間とネズミだけではなくチンパンジーや犬などの動物でもやっていて、その反応もまた面白いものがありますよ。
でもこうして考えるうちに、「人の心」も「動物の心」も、みんな根は同じなんだな、と感じさせてくれます。人の心もずっと昔の動物のころから進化してきたのですね。
※このブログは「70過ぎてのお勉強」シリーズの一環です。
※正確な事実はご自身の責任でお調べください。内容をうのみにしないでください。
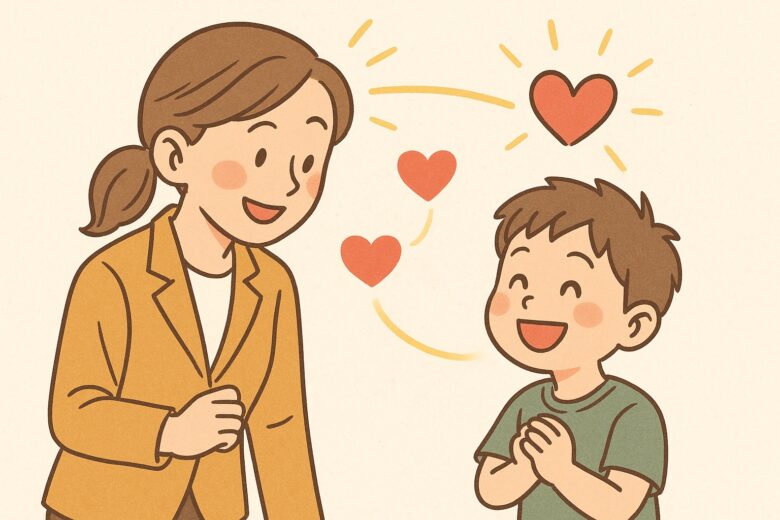



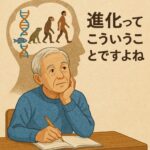
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません