研究レポート77・年功序列と群れの心
77歳になって、あらためて「研究ごっこ」を始めてみました。
タイトルは勝手に《研究レポート77》。
人の心や動物の行動、進化、そして「命ってなんだろう」という感覚を、自分なりに見つめ直すノートです。
日本の職場にあった「年功序列」
最近のニュースで、新入社員のあいだに「年功序列が望ましい」という声が増えていると耳にしました。
かつての日本企業は、新人教育に1年以上かけることもありました。
その前提には「社員は一生この会社で働く」という暗黙の約束があり、その中で技術や文化が受け継がれていったのです。
たしかに不公平さもありましたが、見方を変えれば「能力に応じて働き、必要に応じて受け取る」という助け合いの仕組み。
私はそこに「なるほど、まるで家族のようだ」と感じました。

群れの中の役割分担
自然界を見ても、群れの中には役割の偏りがあります。
オオカミは狩りが得意な個体が前に出て、他の個体は後ろで群れを守る。
アリの社会も、一部が働き、他が巣を維持する役目を果たしています。
人間の年功序列も、そんな「群れで生きる仕組み」のひとつだったのかもしれません。
だからこそ多くの人が「皆中流」という感覚を共有できたのでしょう。
今日ためしてみたいこと
今日の小さな実験として、あなたの生活の中で「群れの安心」と「競争の強さ」を1つずつ探してみてください。
群れの安心 → 家族の食卓での役割分担、会社の飲み会の雰囲気、地域の行事など。
競争の強さ → 成績や売上のランキング、職場での評価、SNSのフォロワー数など。
そのうえで、「今日は安心を優先してみよう」「今日はあえて競争に挑んでみよう」と、自分でバランスを選んでみる。
たった一日の試みでも、自分がどちらに傾きやすいか、意外な気づきが得られるかもしれません。
今日の気づき
年功序列のしくみは「群れの安心」を守る工夫でもあった。
安心と競争、そのバランスを選ぶのは、私たち自身の小さな行動なのかもしれない。
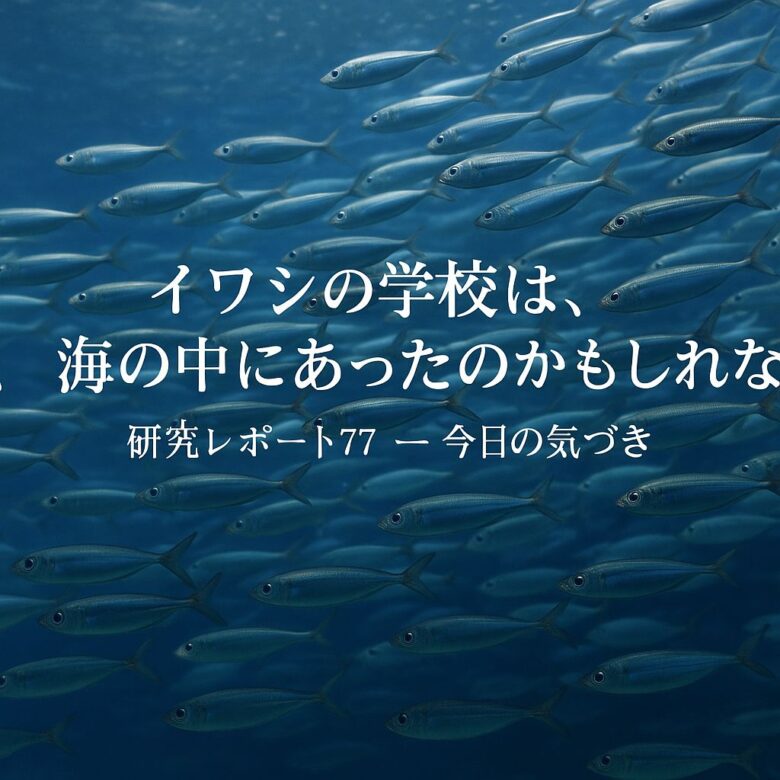

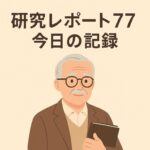


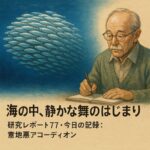
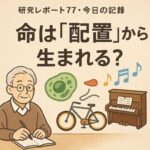
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません