快を求め、苦を避ける ― 心の原点はDNAにあった(研究レポート77)
この記事でわかること
「快を求め、苦を避ける」という行動は人間に限らず、生物全体に共通する基本原理です。その起源をDNAの働きにまでさかのぼり、心の根っこを考えます。
生物に共通する行動原理
私たち人間は美味しいものを食べて喜び、痛みを避けて行動を変えます。
これは心理学でいう「快楽原則」にも通じますが、実は動物だけでなく微生物にも同じ行動パターンが見られます。
DNAレベルで仕組まれた反応
単細胞生物であるゾウリムシは、酸性の刺激を受けると反射的に逃げ、栄養の多い方向には集まります。
これは「考えた結果」ではなく、DNAに組み込まれた化学反応の連鎖にすぎません。
米国の研究では、線虫 C. elegans が温度の変化を感じ取り、餌のある適温を選んで移動することが観察されました。わずか神経細胞302個の生物が、快を求め、苦を避ける行動をとるのです。
また、東京大学の研究グループは、ショウジョウバエの幼虫に光刺激を与える実験を行い、好む光の強さと避ける光の強さに個体差があることを報告しました。これは「快と苦の基準」がDNAのわずかな違いによって変化することを示しています。つまり、快・不快の判断は偶然ではなく、遺伝子レベルで設定されているのです。
心の根っこはどこにあるのか
私たちの「嬉しい」「嫌だ」という感情も、進化の歴史をさかのぼれば、こうした単純な反応の延長線上にあります。
DNAが作り出す化学的な仕組みが積み重なり、複雑な脳や神経ができ、やがて「心」と呼ばれるものが形づくられたのでしょう。
つまり、私たちの行動の奥には「快・不快」という最もシンプルな基準が流れているのです。
勉強も、仕事も、人間関係も、「快を求め、苦を避ける」という根本の回路が働いています。
今日の気づき
心の深い働きも、その始まりは「快」と「苦」の二択にあった。
私たちはDNAが刻んだ原理の上に心を築いているのかもしれない。
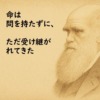
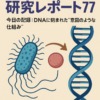


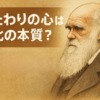

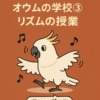

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません