スズメの学校 ― 文化を受け継ぐ小さな声(研究レポート77)
この記事でわかること
身近なスズメにも「方言」があり、それが世代を超えて受け継がれる“文化”となっていることをご紹介します。人間の言語や文化とのつながりを考えるヒントになります。
スズメの鳴き声にも方言がある
スズメの鳴き声は全国どこでも同じように聞こえますが、研究によると地域ごとに少しずつ違う「方言」があることが分かっています。
例えば、ある地域のスズメは短いリズムで仲間を呼び、別の地域では長めのフレーズを使う。この違いは偶然ではなく、世代を超えて受け継がれる音の文化なのです。
鳴き声が“文化”として伝わる
ヒナは親や仲間の声を聞いて育ち、その群れ特有の発声を身につけます。つまり「学校」に通うようにして、スズメは地域の鳴き方を学んでいるのです。
さらに驚くのは、群れを移動したスズメが新しい地域の鳴き声を覚え直すこと。これは人間が転校して新しい方言に慣れていく姿とよく似ています。
研究者の調査によれば、スズメの鳴き声の違いは数十年単位で受け継がれ、方言が文化として定着することが確認されています。
例えば京都大学の研究では、都市部と農村部で暮らすスズメの鳴き声を比較すると、同じ「警戒の声」でも都市部は高めで短い音、農村部は低めで長い音になる傾向が観察されました。これは周囲の騒音や環境に合わせて声が調整され、その後ヒナに受け継がれることで“地域の方言”として固定されると考えられています。
人間の文化との共通点
人間の言語も「意味は共通」でも「発音や表現は地域ごとに違う」という特徴があります。
例えば「犬の鳴き声」を日本では「ワンワン」と表現しますが、英語では「bow-wow」、フランス語では「ouaf」。意味は同じでも表現は異なるのです。
スズメの世界でも、危険を知らせたり仲間を呼んだりといった基本の意味は共通。ただしその具体的な鳴き方は地域によって異なります。
つまり、スズメたちも「自分たちの仲間かどうか」を鳴き声の方言で確かめ合っているのかもしれません。
今日の気づき
小さなスズメの声も、ただの音ではなく文化の証。
方言は、仲間をつなぎ世代を超えて伝わる“学校の教科書”だった。
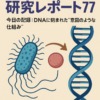
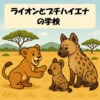
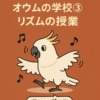




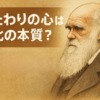
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません