進化と「子どもを欲しい」という気持ち ― 衝動と文化のはざまで(研究レポート77)
この記事でわかること
進化の本質は「子孫を残すこと」だとよく言われます。しかし人間社会では「子どもを欲しい」という気持ちそのものが多様になっています。進化と感情の関係を整理してみます。
進化の定義は「子孫が繁栄すること」
放送大学の授業で「進化とは子孫が繁栄すること」と説明されていました。
これはダーウィン以来の考え方で、どれほど立派に生きても子孫を残さなければ進化の流れからは消えてしまうというものです。
シンプルですが、命の長い歴史を振り返ると確かに本質を突いています。
子どもを欲しがらない人もいる
現代社会では「子どもはいらない」と考える人も少なくありません。
進化の原則から見れば不思議に思えますが、実は「子どもを欲しい」という感情は進化の必然ではないのです。
心理学や社会学の調査でも、「子どもを望むかどうか」は文化や時代背景に強く影響されることが分かっています。
例えば国立社会保障・人口問題研究所の調査では、日本の若い世代の約3割が「子どもを持たなくてもよい」と回答しています。この割合は数十年前に比べて増加しており、経済状況やライフスタイルの変化が大きく影響していると考えられます。
本能は「性の衝動」にある
生命史を振り返ると、進化を動かしてきたのは「子どもを持ちたい」という意識的な感情ではなく、もっと原始的な「性の衝動」です。
例えばサケは一生の最後に川を遡って産卵しますが、そこに「子どもを育てたい」という意識があるわけではなく、DNAに刻まれた衝動に従っているだけです。
人間も同様に、性欲や親密さを求める気持ちの延長に子どもが生まれ、結果的に子孫が残ってきました。
つまり「子どもを欲しい」という気持ちは文化や社会の中で意味づけられた感情であり、進化の本質はよりシンプルな「生殖行動」にあります。
進化心理学の研究でも、「子どもを持ちたい」という願望は遺伝子そのものではなく、社会的な報酬や価値観の影響で強まると説明されています。言い換えれば“本能”ではなく、“文化的な意味づけ”が強調されているのです。
今日の気づき
「子どもを欲しい」という感情は文化が生み出した産物。
進化を動かしてきたのは、もっと原始的な衝動だった。
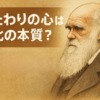

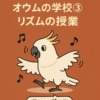

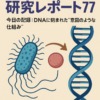



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません