研究レポート77・オウムの学校③ リズムの授業
この記事でわかること
音楽に合わせて踊るオウムの行動から、リズム感と学習能力の関係を考えます。動物行動学の研究を通して「音楽と心」の不思議な結びつきを探ります。
音楽に合わせて踊る動物は珍しい
人間は自然に音楽に合わせて体を動かしますが、動物で同じことができる例はごく限られています。
その代表例がオウムです。特に有名なのが、アメリカで研究対象になったキバタンの「スノーボール」。音楽に合わせて首を振ったり足踏みしたりする姿は、世界中の研究者を驚かせました。
テンポに合わせて動きを変える
スノーボールの研究では、音楽のテンポを速くしたり遅くしたりすると、彼もそれに合わせて動きを変えることが確認されました。
これは「ただの反射」ではなく、リズムを認識し、意識的に体を合わせている証拠とされます。
さらに他の研究でも、オウムが人間のダンスを観察してから真似をする行動が記録されています。つまりオウムは「リズムを感じ取る」だけでなく「学んで応用する」力を持っているのです。
参考動画:音楽に合わせて踊るオウム「スノーボール」
以下の動画は、研究対象となったキバタンのスノーボールが音楽に合わせて踊る様子です。テンポを変えてもリズムを合わせようとする姿が記録されています。
この映像は「動物もリズム感を持ち得る」という研究を象徴する貴重な例です。
リズムと社会性の関係
なぜオウムがリズムに合わせられるのでしょうか。研究者はその理由を「声真似」と関係づけています。
オウムは仲間の声を学習する高度な能力を持ちます。この「音を模倣する仕組み」がリズム感にも応用され、音楽に合わせて体を動かすことを可能にしていると考えられています。
人間もまた、リズムに合わせて一緒に歌ったり踊ったりすることで仲間意識を強めてきました。
オウムのダンスも、仲間と調和するための“社会的な機能”を反映しているのかもしれません。
今日の気づき
オウムのダンスは遊び心だけではなく、学習と社会性の証だった。
リズムに身をゆだねる行為は、人間とオウムをつなぐ共通の文化かもしれない。

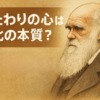
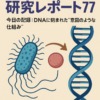
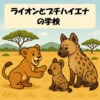



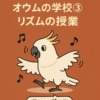
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません