ライオンの狩りの練習 ― 遊びは教育
研究レポート77・動物たちの学校⑩中等科
ライオンの狩りの練習 ― 遊びは教育

朝のサバンナに、金色の光が広がる。
草の先が風に揺れ、朝露が小さく光る。
その中で、子ライオンたちは取っ組み合って転がっていた。
それは無邪気な遊びに見えるが、実はもう「授業」が始まっている。
彼らは生まれてすぐに、群れの中で“生きる技術”を学び始める。
遊びながら噛む力を確かめ、倒されても立ち上がり、
仲間との距離を少しずつ測っていく。
タンザニア・セレンゲティ国立公園で40年以上続く長期観察(Craig Packer研究チーム)でも、
子ライオンたちが遊びを通じて筋力や反射、仲間との呼吸を学ぶ様子が報告されている。
遊びは、命を支える訓練なのだ。
1.遊びの意味 ― 無駄の中に隠れた準備運動
子どもライオンの遊びは、見ていて飽きない。
尻尾を追いかけたり、仲間の背中に飛び乗ったり。
一見、無駄な動きの連続だ。
しかし、動物行動学者マリアン・ドーキンスらの研究によると、
この「プレイ行動」には、身体感覚と神経の連携を育てる大きな意味がある。
遊びは“神経系の練習台”であり、失敗できる安全な環境だ。
だから、転んでも笑っていられる。
その繰り返しが、やがて“狩りの動き”へとつながっていく。

2.兄弟・姉妹の先生たち ― 群れで育てる教育
昼のサバンナでは、年上の兄や姉が小さな子を相手に遊びを仕掛ける。
体を低く構え、じっとにらみ合う。
そして突然、飛びかかる。
倒された弟がうなり声を上げると、兄はわざと力を抜く。
次にどんな反応をするかを見守るように。
言葉はない。けれど、確かに“教えている”のだ。
この光景はセレンゲティの観察記録(Packer & Pusey, Behavioral Ecology, 1995)にも数多く記録されている。
兄姉が弟妹の訓練を手伝い、狩りの基本姿勢やタイミングを自然に伝えていく。
つまり、群れ全体がひとつの学校なのだ。
人間の兄弟にも似た光景がある。
上の子が下の子に遊びを教え、失敗を笑い合う。
教科書はなくても、そこに確かな「教育」がある。
3.母の視線 ― 教えない教育
午後の強い日差しの下、母ライオンは木陰に横たわる。
子どもが近づきすぎると、母はわずかに目を動かす。
その一瞬で、子は止まる。
それだけで“教え”が伝わる。
母は叱らない。
ただ見ているだけだ。
この沈黙の教育こそ、野生の信頼のかたちだ。
セレンゲティでの行動観察(Elliott & Ginsberg, 2000)では、
母ライオンが子の行動を静かに見守る「間接的教育」の重要性が指摘されている。
危険を避けるより、経験を積ませる方を選ぶ――それが自然の教育哲学だ。
人間社会でも似た瞬間がある。
子どもの失敗を見守る勇気。
母ライオンのまなざしは、まるでその象徴のようだ。

4.遊びから狩りへ ― リズムを合わせる訓練
夕方、空が黄金色に染まるころ。
母が静かに立ち上がる。
風上でインパラの群れが動くのを見て、姿勢を低くする。
子どもたちは息を潜め、母の動きを真似る。
足音を消す。
草の影に体を沈める。
そして、母が一歩動くたびに同じ方向へずれる。
これは単なる狩りの練習ではない。
「呼吸を合わせる」訓練なのだ。
Craig Packer(Serengeti Lion Project)のフィールドノートにも、
子どもたちが母の模倣を通じて群れの“狩りリズム”を体で学ぶ過程が詳しく描かれている。
狩りの成功よりも、調和の感覚こそが次の命を支える。
獲物を逃してもいい。
大切なのは、リズムを共有すること。
風を読み、仲間と歩調を合わせる力があれば、彼らは必ず生き残る。
5.群れで生きるという知恵 ― 狩りを超えた学び
翌朝、群れは再び動き出す。
日差しの中で、メスたちは互いに体を寄せ合い、
若いオスが子どもを見守っている。
セレンゲティの研究チームによる長期調査(Packer et al., 2019, Ecology Letters)では、
群れの秩序が「順位」よりも「協調」で保たれていることが報告されている。
待つこと、譲ること、リズムを乱さないこと――
その見えないルールが、群れの安定をつくっている。
食事の順番も、決して争いでは決まらない。
年長のメスが先に食べ、子どもはその合図を待つ。
その「待つ時間」もまた、教育の一部なのだ。
人間社会にも似ている。
誰かが話すとき、他の人が静かに聞く。
それは“群れのマナー”であり、“社会の知恵”だ。
ライオンたちは、静かにそのことを教えてくれる。

今日の気づき ― 遊びは、生きる力の原点
サバンナの夕暮れ。
母ライオンが歩き出すと、子どもたちがついていく。
足跡が草の間に並び、同じ方向に消えていく。
遊びも、狩りも、休息も、すべてが「生きる練習」。
教科書もテストもいらない。
ただ、風と仲間と命の鼓動があれば、それでいい。
遊びは、命が命をつなぐための最初の授業。
その教室は、いまもサバンナの風の中に広がっている。
参考情報
- Craig Packer & Anne Pusey, Behavioral Ecology of Lions in the Serengeti, 1995.
- Serengeti Lion Project (University of Minnesota, 1980–現在)
- M. Dawkins, Animal Behaviour: A Very Short Introduction, 2012.
- 岩合光昭『ライオンの家族』(小学館, 2012)
- National Geographic, “Lions: Lessons in Survival”, 2019.

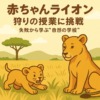

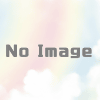
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません