ライオンは怖い?
研究レポート77・動物たちの学校②初等科
ライオンは怖い?

ライオン――その名前を聞くだけで、胸の奥に少し緊張が走ります。
子どものころから絵本やテレビで、彼らは「百獣の王」として描かれてきました。
力強い体、鋭い牙、広い草原を睨み渡す金色の瞳。
人間の想像の中で、ライオンはいつも“恐怖と威厳の象徴”でした。
ところが、そんな私たちの常識を静かにくつがえすような言葉を、
動物写真家の岩合光昭さんが残しています。
「ライオンを怖いと思ったことは、一度もない。」
この一文に出会ったとき、私は思わず本を閉じて考え込みました。
あのライオンを、怖くない? 本気で?
多くの人が“信じられない”と感じるのではないでしょうか。
けれど、ページをめくるうちに、岩合さんの言葉の奥にある意味が見えてきました。
彼が言う「ライオン」とは、人の手によって飼育されているライオンではなく、
野生の中で自由に生きるライオンたちのことなのです。
野生という教室

岩合さんは、サバンナの地平線の向こうに沈む太陽を追いながら、
長い時間をかけて“野生の授業”を見つめてきた人です。
その視線の先にあるのは、単なる“猛獣”ではなく、
ルールを持ち、家族を守り、静かに共存する生き物たちの社会。
ライオンは人間を滅多に襲いません。
それは、牙が鈍ったからでも、気性が穏やかだからでもありません。
むしろ、彼らは生きるために“襲わないこと”を学んできたのです。
人間がライオンを怖がるように、
ライオンもまた人間を“怖い存在”として認識しています。
彼らにとって、人間は“触れてはいけない相手”。
長い年月の中で、そう学び、そう伝えてきたのです。
もし、人間を常食とするライオンの群れが存在したなら――
おそらくその群れはとうの昔に絶滅していたでしょう。
“人間を襲わない”という文化を持つライオンこそが、
結果的に生き延びてきたのです。

群れの教育
ライオンの子どもたちは、生まれながらにして狩りが上手なわけではありません。
最初は母親のそばで転げまわるだけ。
けれど、日々の観察の中で「生き方」を少しずつ吸収していきます。
母親が草の中で身を低くし、じっと息を潜める。
その緊張感を、子どもは小さな体で感じ取ります。
やがてシマウマやヌーが走る姿を見ると、
心の奥に何かが火をつけられるように「狩りのスイッチ」が入る。
でも、人間を見ても、母は動かない。
その静けさの中に、“これは違う”という学びが刻まれます。
それは言葉のない授業。
そしてその授業が、ライオンの文化を形づくるのです。
この「学びの連鎖」がある限り、
ライオンは人間を襲わない。
それが、彼らの社会の中で受け継がれてきた知恵なのです。
野生と飼育のあいだ
ここで勘違いしてはいけないのは、
岩合さんの「怖くない」は、野生のライオンに対しての言葉だということ。
動物園や撮影用に飼われたライオンは、
すでにその“教育の系統”から外れています。
野生の群れの中で育った個体は、人間との距離を知っています。
近づきすぎれば危険、追えば逃げる、
その感覚を、母から学び、群れの中で磨いてきました。
一方、人間が関わって育てたライオンは、
その“距離の感覚”が曖昧になります。
だから、同じライオンでも、
人間社会に近い個体と野生の個体では“怖さの意味”がまったく違うのです。
岩合さんが語る「怖くない」は、
人間の支配が及ばない大地で、
ライオンがライオンらしく生きる世界の話。
そこには、互いに領分を尊重する“自然のルール”が存在するのです。
サバンナの共存関係
ライオンだけではありません。
サバンナでは、ハイエナ、チーター、ゾウ、シマウマ……
さまざまな生き物たちが一つの舞台を共有しています。
たとえばライオンとハイエナ。
彼らはしばしば獲物をめぐって衝突しますが、
互いを“食べる対象”とは見なしません。
あれほどの力を持ちながらも、
「相手そのものを獲物にしない」という不文律を守っている。
それは、進化の過程で得た“生き残るための知恵”です。
もし彼らが互いを食べ合っていたら、
どちらの種も、今のようには繁栄できなかったでしょう。
自然の中では、戦うより、避ける方が生き延びる。
そのシンプルな原理を、動物たちは体験の中で学んできたのです。
恐れは知恵のかたち
私たちはライオンを「怖い」と感じます。
それは当然です。
鋭い爪、太い前足、咆哮の一声――
あらゆるものが“生きる力の象徴”のように見えるからです。
でも、ライオンもまた人間を怖がっています。
銃の音、車のエンジン、金属の匂い。
そのすべてを、“危険のサイン”として学び取っています。
恐怖とは、ただの感情ではありません。
それは、生き延びるためのセンサー。
本能と経験のあいだで、磨かれていく知恵なのです。
人間は「知らないから怖い」。
ライオンは「知っているから怖い」。
この違いを思うと、
恐れというのは“学びのもう一つの形”なのだと感じます。
学ぶ力が生存をつくる
ライオンの社会では、教育が“生き延びるための文化”です。
どの獲物を追うか、どの相手を避けるか。
それを、親や群れの中で体で学んでいきます。
そして、人間もまた同じです。
危険を避け、他者と共存する方法を、
家庭や学校、社会の中で少しずつ身につけていきます。
だから私は思うのです。
学びとは、命の続き方そのものなのではないかと。
それは言葉を超えて、種を超えて、
あらゆる生き物に共通する“生存の技術”です。
ライオンを見つめながら考えたこと
サバンナの夕暮れ。
岩合さんの映像で見た、あの黄金色の草原を思い出します。
母ライオンの足もとに転がる子ども。
やがてその子が立ち上がり、母のあとを追って歩き出す。
その一歩一歩に、“学び”が宿っているように思えます。
倒れること、あきらめないこと、
そして、他者を恐れすぎないこと。
すべてが“生きる授業”の一部なのです。

今日の気づき
「ライオンは怖い?」
この問いの答えを、今の私は少し変えたいと思います。
「怖くない、でも尊敬している。」
岩合光昭さんが語った“怖くないライオン”は、
人間と距離を保ちながら、知恵で共存してきた野生のライオン。
その背中には、力よりも“学び”の重さが見えます。
ライオンが人間を襲わないのは、牙が鈍いからではなく、
群れの中で育まれた“生存のルール”があるから。
そして、私たち人間もまた、
その延長線上で生きている――。
そう考えると、サバンナの風景が、少し違って見えてきます。
そこには恐れよりも、
静かな尊敬と、つながりの温かさが広がっているのです。
参考文献:岩合光昭『生きもののおきて』ちくま文庫(2010)



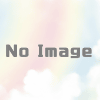


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません