クレバーハンスと「信じる力」
研究レポート77・動物たちの学校⑬高等科
クレバーハンスと「信じる力」

1.馬が問いかけた「心の会話」
ある日、古いドキュメンタリー番組で、一頭の馬が人間の質問に“答えている”映像を見ました。 その名はクレバーハンス。20世紀初頭、ドイツ・ベルリンで話題をさらった馬です。
ハンスは、老教師フォン・オステンの愛馬でした。 主人が「1+1=?」と尋ねると、ハンスは地面を2回コツコツと叩きます。 しかも、それだけではありません。足で数字を示したり、日付や名前を選んだりと、まるで「人間のように考えている」かのようでした。
当時の新聞は「奇跡の馬」「動物界の天才」と報じ、人々は連日、ベルリン郊外の広場に集まりました。 帽子を脱ぎ、固唾をのんで見守る観衆の前で、ハンスは落ち着いて答えを出します。 その様子に、子どもたちは歓声を上げ、大人たちは驚きと尊敬をこめた目で見つめたといいます。

しかし、科学者たちは冷静でした。 彼らはこの不思議な現象を解き明かそうと、実験を繰り返しました。 その結果、ハンスは「言葉」を理解していたのではなく、「人間のわずかな体の動き」を読み取っていたのです。
質問者が正解を知っているとき、体が少し前のめりになったり、息を止めたりする。 そのほんの一瞬の変化をハンスは感じ取り、足を止めた――。 つまり、ハンスは人間の「心の影」を見ていたのです。
私はこの話を初めて知ったとき、「これは単なる動物の賢さではない」と感じました。 言葉を使わなくても、通じ合うことがある。 クレバーハンスは、人と動物のあいだに確かに存在する“沈黙の会話”を見せてくれた気がします。
2.無意識が語る ― クレバーハンスの教訓
人間は意識していなくても、顔の筋肉、姿勢、呼吸、視線のわずかな動きで多くを伝えています。 私たちはそれを普段、意識していませんが、相手にはちゃんと伝わっているのかもしれません。
心理学では、このような現象を「実験者効果」と呼びます。 研究者の期待や思い込みが、被験体の行動を変えてしまう。 クレバーハンスの例は、まさにその典型でした。
けれども私は、この現象を「誤差」として片づけたくはありません。 むしろ「生きもの同士の共鳴」として考えたいのです。 人が“信じた”瞬間に、馬もそれを感じ取って動いたのなら、そこには「信頼」という目に見えない糸が働いていたのではないでしょうか。
ハンスが足を叩くたびに、会場の空気がわずかに揺れ、観客も息をのんだことでしょう。 その緊張と期待が、ハンスの心にも伝わっていたとしたら――。 「信じること」が行動を引き出した、まさにピグマリオン効果の原型です。
この話を知ってから、私は「無意識の会話」というものを意識するようになりました。 言葉で励ますよりも、目線や沈黙が何かを伝えることがある。 たとえば、親が子に向けるまなざし、教師が生徒を見守る姿勢。 そこには、「あなたならできる」という無言のメッセージが込められている気がします。
3.言葉のないコミュニケーション ― 進化が育てた読む力
動物たちの行動を観察すると、この「読む力」がいかに進化の中で磨かれてきたかがわかります。 馬の群れでは、一頭の耳の角度がわずかに変わるだけで、仲間が一斉に方向を変えることがあります。 危険を察知したリーダーの微妙な緊張を、他の個体がすぐに感じ取るのです。

犬は、人の指差しや目線の方向を理解し、隠された食べ物の位置を推測できます。 カラスは危険な人の顔を覚え、仲間に伝えます。 オウムは飼い主の声の抑揚から感情を読み取り、その日ごとに反応を変えることがあります。
こうした例を見ると、「読む力」は言葉に先立つもっと根源的な“知性”であることがわかります。 言葉がなくても、目や体、距離感で通じ合える世界。 それこそが、生きものの基本的なコミュニケーションの形なのかもしれません。
人間の社会でも、同じようなやりとりが行われています。 会議の場で誰かが発言しようとしたとき、周囲の空気が一瞬止まる。 舞台俳優が台詞を発する直前の“間”に、観客の心が引き込まれる。 それは言葉以上のやり取り――「体と言葉のあいだにある情報」です。 もしかすると、人間が複雑な言語を発達させる過程で、この無意識的な“読む力”が少しずつ衰えたのかもしれません。 けれど、動物との関係や子どもとの触れ合いの中で、それはいまも確かに息づいています。
4.「信じる力」はコミュニケーションだった
クレバーハンスの物語が教えてくれるのは、「信じること」そのものがコミュニケーションの一形態だということです。 ハンスが動いたのは、命令ではなく、見つめる人の“信じるまなざし”を感じ取ったから。

のちに心理学では、この力が「ピグマリオン効果」として知られるようになりました。 教師が生徒を信じるとき、生徒はその信頼に応えようと努力します。 逆に「どうせ無理だ」と思われたとき、人は無意識のうちに自信を失っていきます。
この仕組みは、人間同士だけでなく、動物との関係にも共通しています。 飼い主が犬に「できる」と信じて接するとき、犬はそれを敏感に察し、挑戦をやめません。 信頼とは、目には見えないけれど確実に伝わる“期待のエネルギー”なのです。
信じることは、行動を導く力であり、理解を深める最初のコミュニケーション。 それは、進化の過程で育まれてきた「最古の教育言語」だと思います。 クレバーハンスの姿には、その原型が静かに映し出されているようです。
5.今日の気づき ― 教えることは、信じること
教えるとは、知識を与えることではなく、まず「信じる」ことから始まる。 信頼されることで、相手は自ら動き出します。 それはまるで、ハンスが人の期待を感じ取って足を動かしたように。 私たちが誰かに何かを教えるとき、あるいは支えるとき、必要なのは完璧な説明ではなく、静かな信頼なのだと感じます。
クレバーハンスの物語を思い出すと、「信じる力」は特別な才能ではなく、すべての生きものが生まれながらに持っている“対話のかたち”だと感じます。 言葉を超えたところで、私たちはすでに互いに語り合っているのです。
参考文献
O. Pfungst『Clever Hans (The Horse of Mr. von Osten)』(1907)/Rosenthal『Experimenter Effects in Behavioral Research』(1963)
観察地:ベルリン(クレバーハンス実験)ほか


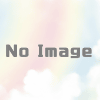

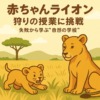
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません