研究レポート77・メダカの学校は本当に学校だった?
77歳になって、あらためて「研究ごっこ」を始めてみました。
タイトルは勝手に《研究レポート77》。
人の心や動物の行動、進化、そして「命ってなんだろう」という感覚を、自分なりに見つめ直すノートです。
童謡に歌われた「めだかの学校」
「めだかの学校」という童謡をご存じでしょうか。
♪めだかの学校は〜川の中〜♪ と、子どもたちが歌うあの優しいメロディです。
歌詞には「誰が生徒か先生か、わからないくらい仲良く遊んでいる」とあります。
小さな魚たちが仲良く群れて泳ぐ姿を「学校」に見立てた、なんとも平和な世界。
私はこれまで「微笑ましい比喩」程度に思っていました。
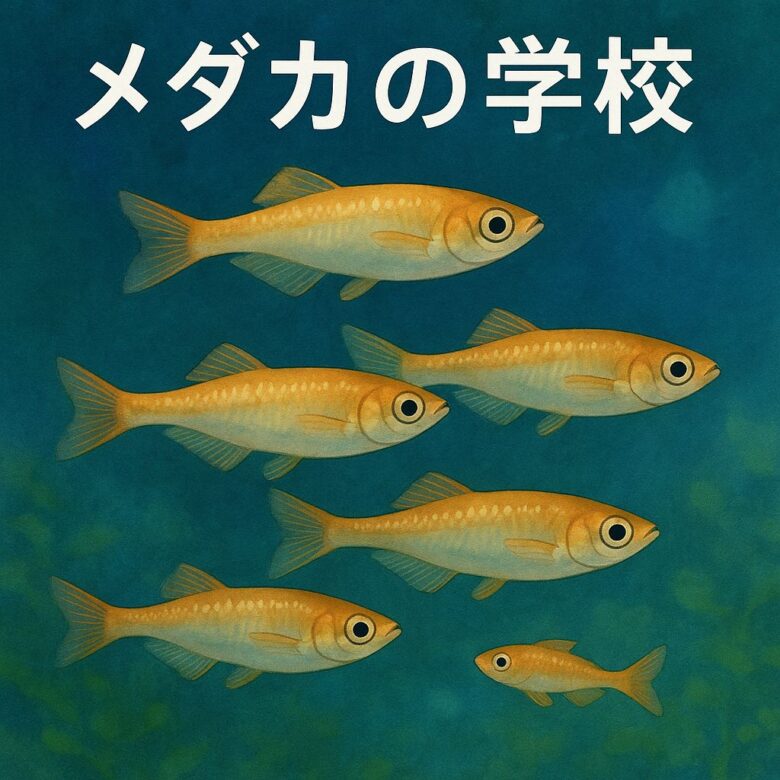
ところが、調べてみると――メダカの群れには、本当に“学校”的な役割があることが分かってきたのです。
仲間を見分ける力
メダカは数匹から数十匹で群れをつくります。
でもその群れは、ただ集まっているだけではありません。
メダカは 仲間を見分ける力 を持っています。
模様や体の大きさ、さらにはにおいまで手がかりにして、同じ仲間を認識し合うのです。
なぜそんなことをするのでしょう?
それは、知らない魚や別の種類と混ざると、動きがそろわず危険が増すからです。
仲間を見分けて行動を合わせることは、生き延びるために欠かせない知恵なのです。
本当の「学校」の役割
本当の「学校」の役割
群れをつくることには、ほかにもさまざまなメリットがあります。
外敵からの防御(仲間が多ければ狙われにくい)
水の流れを利用して省エネ(ひとりで泳ぐより楽)
幼魚同士で泳ぎのリズムを合わせる「練習の場」
繁殖のときに正しい相手を見つけやすい
まるで人間の学校が「安全」「協力」「練習」「出会い」の場になっているように、メダカの群れもまた学校として機能していたのです。
今日ためしてみたいこと
今日の小さな実験として――
「あなたにとっての“学校”とは何ですか?」と考えてみませんか。
教室での学びかもしれないし、職場や地域のコミュニティかもしれません。
あるいは、仲間と安心して一緒にいることそのものが「学校」なのかもしれません。
今日の気づき
「めだかの学校」はただの童謡ではなく、本当に命を支える学校だった。
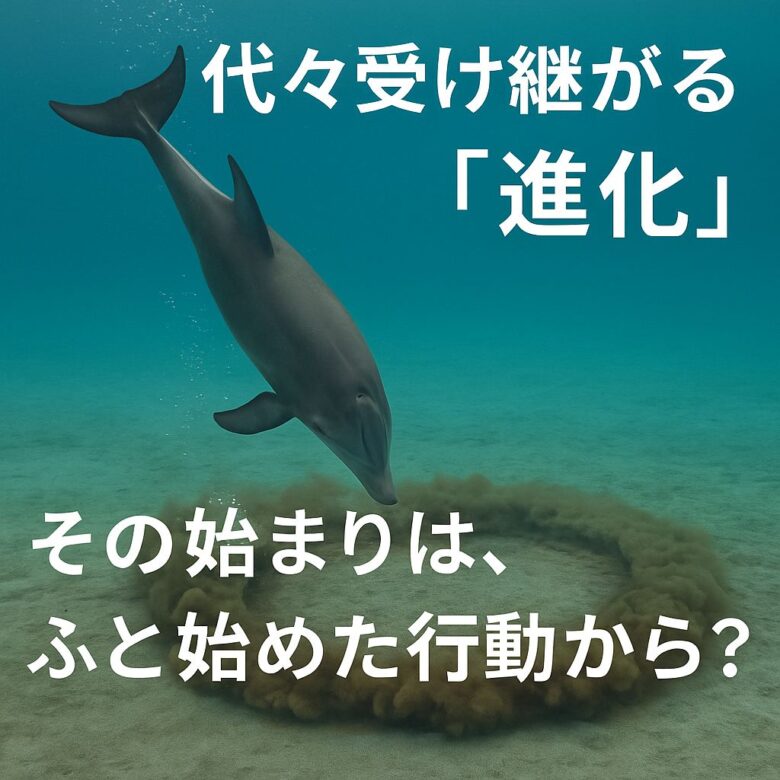


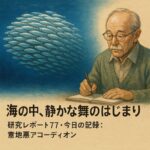

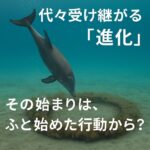



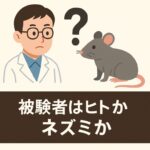
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません