研究レポート77・被験者はヒトかネズミか
77歳になって、あらためて「研究ごっこ」を始めてみました。
タイトルは勝手に《研究レポート77》。
人の心や動物の行動、進化、そして「命ってなんだろう」という感覚を、自分なりに見つめ直すノートです。
実験の裏側を想像する
心理学の教科書を読むと、よく「ネズミを使った実験」や「学生を対象とした実験」が紹介されています。
結果のグラフや数字はきれいにまとまっているけれど、その裏側には必ず“被験者”がいます。
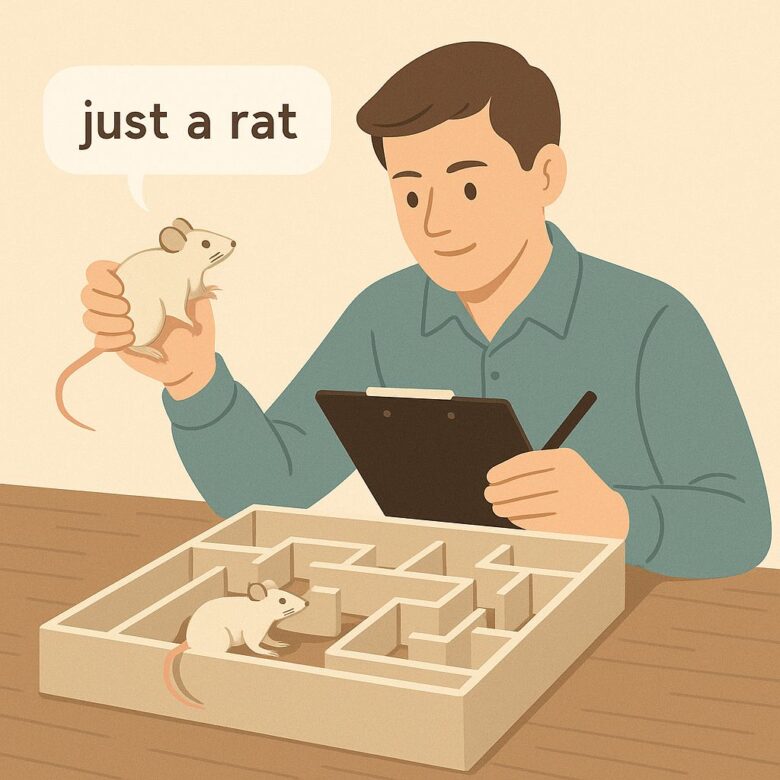
白衣の研究者に導かれて装置に座った学生、狭い迷路を走らされたネズミ。
それぞれが「実験の中の登場人物」として存在していたのです。
私はそこに、単なるデータではなく「個々の命の体験」があることに、ハッとさせられました。
データは中立? それとも人間的?
実験結果は客観的な数字として扱われます。
でも、その数字を生み出したのは、緊張した学生や、迷って立ち止まるネズミ。
彼らの一瞬の戸惑いや、ちょっとした行動が「科学の成果」として記録されていくのです。
そう思うと、科学は冷たいものではなく、むしろ人間的な営みだと感じられます。
今日ためしてみたいこと
今日の小さな実験として、身近な数字やデータの裏側を想像してみませんか?
ニュースで見た「アンケートの結果」
学校や会社で配られる「成績や評価の数値」
健康診断で出てくる「体の数値」
その一つひとつに、必ず人がいて、体験があって、物語がある。
「これは誰のどんな行動の結果なんだろう?」と考えるだけで、数字が少し違って見えてくるはずです。
今日の気づき
数字やデータの裏には、必ず人や生き物の体験がある。
それを思い描くことで、科学はより人間的に感じられる。
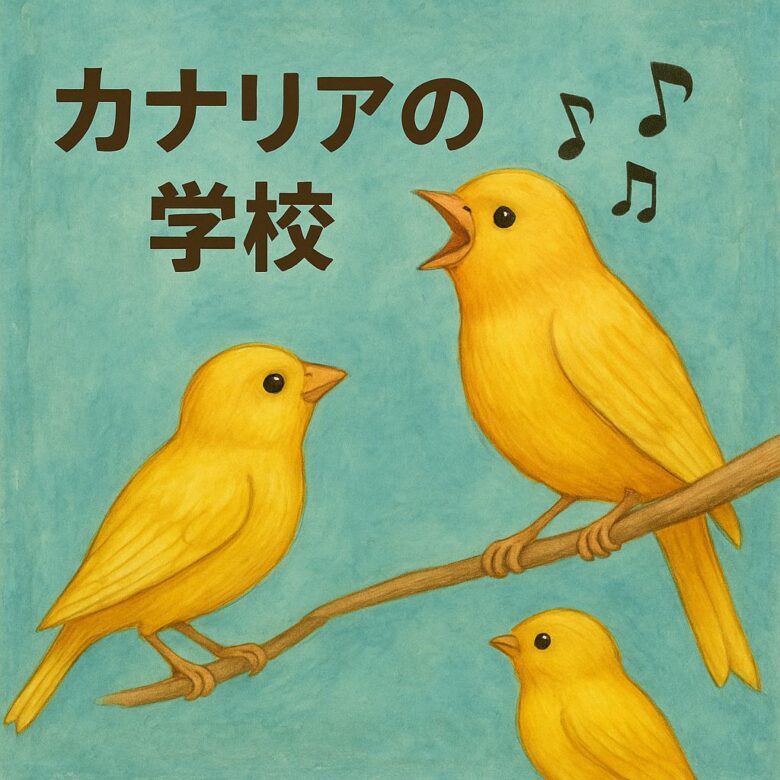
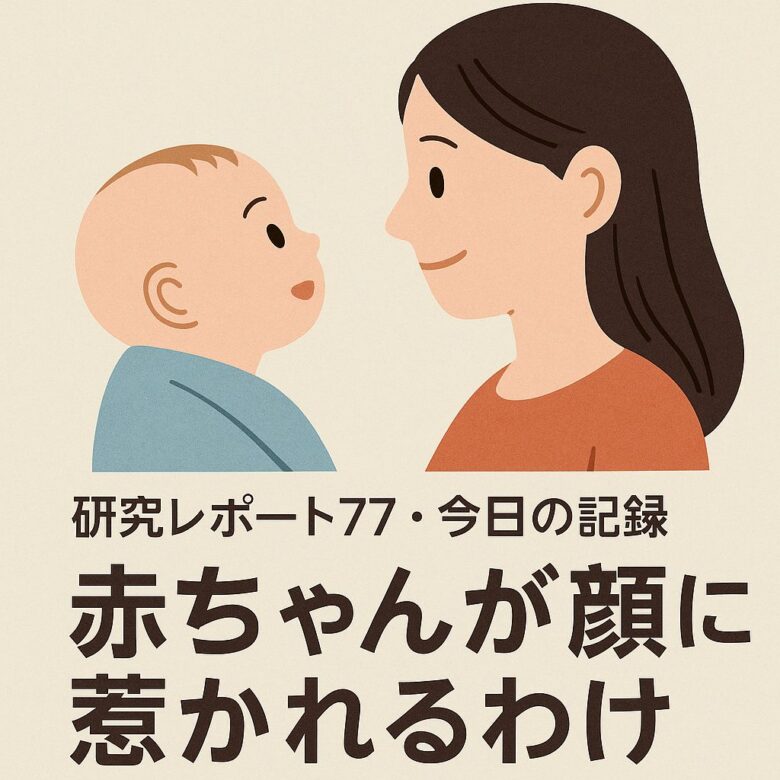


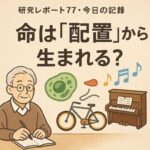


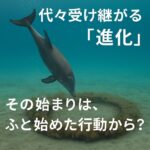


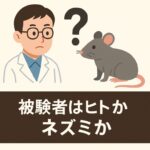
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません