研究レポート77・「見る」とは脳のはたらき?
77歳になって、あらためて「研究ごっこ」を始めてみました。
タイトルは勝手に《研究レポート77》。
人の心や動物の行動、進化、そして「命ってなんだろう」という感覚を、自分なりに見つめ直すノートです。
「目」で見る? それとも「脳」で見る?
「ものを見る」と聞くと、多くの人は「目で見る」と考えがちです。
でも実際には、目はカメラのように光を取り込み、その映像を脳に送っているにすぎません。
本当に「見る」という体験は、脳がその情報を処理して初めて成立します。
形や色を分ける、動きをとらえる、意味を理解する――。
そうした工程を経て、私たちは「見えている」と感じているのです。

臨界期と「見る」
子どもの発達には「臨界期」と呼ばれる大切な時期があるといわれます。
たとえば、幼いころに片目がふさがれたままだと、その目は後で開いても十分に“見る力”を発揮できないことがあります。
目自体は正常でも、脳が「視覚の経験」を得られないまま育つと、情報を処理する仕組みが育ちにくいのです。
つまり「基盤が十分に育たない」ために見え方が制限される――これが臨界期に関連する問題の一例です。
変化していく「見る」
一方で、年齢を重ねるにつれて脳の働きが変化し、見え方が影響を受けることもあります。
アルツハイマー病など脳の病気では、目そのものが問題でなくても「見えにくさ」を感じることがあるのです。
たとえば――
人の顔を見ても誰か分かりにくくなる
物を見ても用途がすぐに結びつかなくなる
こうした現象は「処理の基盤はあっても、その働きが弱まっていく」ことで起こると考えられています。
二つの「見えにくさ」
臨界期 → 「処理の基盤が育ちにくい」
脳の変化 → 「基盤はあるが弱まっていく」
どちらも「見えにくい」という点では共通していますが、その理由は異なります。
それでもはっきりしているのは、「見る」という体験は目だけではなく脳のはたらきに支えられているということです。
今日ためしてみたいこと
今日の小さな実験として――
「私が“見えている”と思っているものは、どこまでが目で、どこからが脳なのか?」と考えてみませんか。
スマホの画面を見て文字を理解するのも、景色の中で友人の顔を見分けるのも。
すべて脳がつくり出す「見る」という体験の一部です。
今日の気づき
「見る」とは目ではなく、脳がつくり出す体験だった。
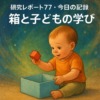





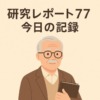
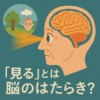


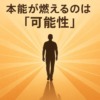
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません